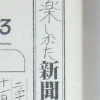|
■坂巻裕一/佐カ間球壱 ■2003- ■1999-2003 ■■shinkan ■■kkq ■■geisai ■■tamajo ■1997-1999 ■1994-1997 ■1991-1994 ■1978-1991 |
このごろ 大学生ごろ 新入生歓迎パンフレット タマビグッズ 多摩美術大学芸術祭実行委員会広報局 2003年多摩美術大学情報デザイン学科卒業研究制作展 〜タマジョー〜 浪人生ごろ 高校生ごろ 中学生ごろ 小学生まで |

|
じぶんのかお 1985.03 うめ組 |
女の子は好んで人形のような人物像を描くのですが、僕は人を描くのがどうも苦手でした。似ないと恥ずかしいという思いが強かったのです。それでもがんばって描いたという感じが、ぎこちない線から伝わってきます。 保育所の修了アルバムより |
 |
おひなさま 1985.03 うめ組 |
保育所が幼稚園と違う点は、教育をしないところだそうです。基本的に、子どもを預かる機能だけのようです。 保育所の修了アルバムより |
 |
ジャンボすべり台 1987 小3 |
小学校の校庭にある築山と通称ジャンボすべり台は、低学年の頃、なかよし(落書き)帳などに何度も描きました。前項のコアラにしてもすべり台にしても、一度気に入ったものを何度も反復して描くのが好きだったようです。 一年生の時の写生会で描いた築山は、市の文化祭用に選ばれました。放課後の教室で先生と残って描いていた時の、差し込む夕日がきれいだったのを覚えています。 |
 |
瓢箪 1987.10.18 小3 |
「ふるさとの秋まつり」の陶芸教室に参加してつくったものです。当時集めていたビックリマンシールのキャラクターである「ヤマト王子」の持っている樽酒に憧れてつくったような気がするのですが、樽ではなく瓢箪なのは何故でしょうか。 |
 |
虫歯予防ポスター 1988 小4 |
テーマの赤い文字を黄色で縁取る方法は、三、四年生の時の担任の荒井先生に教わったもので、この頃よく用いていました。その縁取りも途中までしかやっていませんし、この絵は完成しているのかすら定かではありません。 |
 |
竹笛 |
「のびのび教室」にて。「ボー」という音が出ます。 |
 |
表札 1988.08.01-05 小4 |
「のびのび教室」にて。建て替える前の家では、実際に玄関に取り付けていました。 |
 |
イヌワシ 1988.08 小4 |
夏休みの宿題としての作品です。羽の模様をヘアピンで押して付けたのが工夫した点です。 |
 |
子牛に乗るタイの子ども 1988 小4 |
「読書感想文集」より。ちゃんと署名を入れて自己主張しています。人を描くのは相変わらず苦手でした。 |
 |
花弁型陶器 1988.10.16 小4 |
「ふるさとの秋まつり」にて。 |
 |
つくえ 1989.01.10 小4 |
つくえ係の名簿に書いたものです。 つくえ係というのは、つくえがきちんと並べられているかを調べたり、並べたりする係で、教室の美観を保つ上でとても重要な役割を果たしていたと思います。机を乱したまま帰ってしまった人を放課後に調べて、次の日の朝に注意したりします。もちろん、優秀だった人は学期末に表彰します。 |
 |
自己PR 1988.03 小3 |
すきな科目:理科 すきなこと:手作りの物を作ること ゆめ■■■:体育がじょうずになりたい。 自己PR■:手作りの物を作り、それを自分で使っている。 「3・4年生の思い出」より。 |
 |
ヘビの貯金箱 1989.08 小5 |
夏休みの宿題です。 |
 |
輪島漆器のつくりかた 1989.10 小5 |
家庭学酋長は学習漫画風の内容です。「教える事は学ぶ事」といいますが、まさに第三者に分かりやすく描く事が自分にとっても勉強になっていたのだと思いたいです。 |
 |
家庭学酋長著者之印 1980 小6 |
ビックリマンチョコの台紙に切り刻んだ輪ゴムを瞬間接着剤で止めただけの質素な造りです。 |
 |
親子亀 1989.10.15 小5 |
「ふるさとの秋まつり」にて。何だか亀が好きだったようです。のんびりしているところが似ているからでしょうか。最後には勝ちます。 |
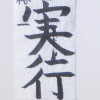 |
計画の実行 1990.01 小5 |
県の書き初め展への出品作品です。 |
 |
くるくるぱー Q1くん 1990 小6 |
教室の窓から見える富士山がお気に入りのQ1くん。しかしある曇り空の日、雲に隠れて富士山が見えなくなってしまい、Q1くんは富士山が死んでしまったのだと勘違いしてしまいます。果たしてQ1くんは富士山に再会することができるのでしょうか。キャスト:Q1くん(黒田治) |
 |
へんたいQ1くん 1990 小6 |
キューリー星からやって来たきゅうり顔のQ1くんと、漫画「ちびまる子ちゃん」のまるちゃんとの掛け合いが面白い、漫才風の話です。 前項との二作品は、当時となりの席に座っていた長谷川宏美さんが描いてくれたものです。 |
 |
七夕集会 1990.06 小6 |
全校規模の印刷物の原稿を描いたのはこれが初めてだと思います。しかし、いったん配付までされた初版に誤字が多すぎたため訂正版がでました。誤字が直されるのは仕方がないと思いましたが、挿し絵の短冊に書いてある願い事の文句も「お金もち おさむ」から「明るく元気な子」に書き換えられてしまっていたのにはとても傷付きました。 |
 |
筆立て 1990.07.29 小6 |
子供会キャンプにて。 |
 |
黒ちゃんの平均点達成作戦 1990.10.28 小6 |
学級紙「ぜいたく新聞」より。 先生がつくるのではなく、生徒がつくる新聞です。そこに頼まれて四コマ漫画を描きました。 媒体の立場をきちんと考慮して、教育系の話をつくりました。 |
 |
半そで半ズボン 1990.03 小6 |
今までがんばってきた事があります。それは、まだ学校を一日も休んでいません。それに、三年生の頃から、半そで半ズボンで、学校へ登校しました。このがまん強さを、西中学校に行ってからも、生かして行きたいと思います。 |
 |
■shinkan ■kkq ■geisai ■tamajo ■2003- ■1999-2003 ■1997-1999 ■1994-1997 ■1991-1994 ■1978-1991 ■sakama91@mac.com |
新入生歓迎パンフレット タマビグッズ 多摩美術大学芸術祭実行委員会広報局 2003年多摩美術大学情報デザイン学科卒業研究制作展 〜タマジョー〜 このごろ 大学生ごろ 浪人生ごろ 高校生ごろ 中学生ごろ 小学生まで |